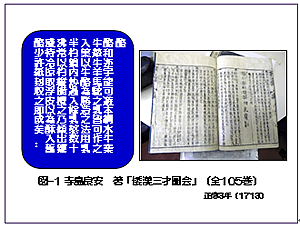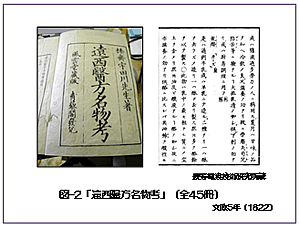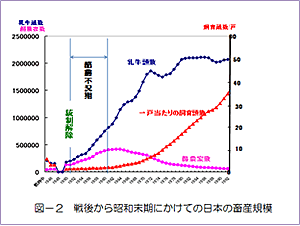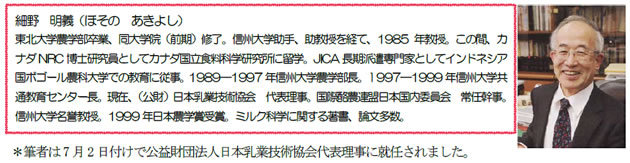1.日本における家畜牛の誕生
古代日本の牛乳利用を語るには、まず古代日本の牛について説明する必要がある。考古学的には日本における牛の存在は数万年前の旧石器時代まで遡ることが出来る。岩手県一関市の金流川(きんりゅうがわ)流域で発見された出土品の中に多量の牛骨化石が含まれており、これらは野牛や原牛の骨であるとされている。しかし、これらの化石牛は日本列島が南北で大陸と陸続きであった洪積世末期に相当することから古代日本で役用や食用に供された家畜牛とは同一の種類は考えられていない。日本における家畜牛の誕生は、縄文中期以降の遺跡から発見される骨こそが家畜牛のものであると推定されており、今日における和牛の祖牛と云われている。しかし、縄文中期以降に飼育されていた和牛はもっぱら労役用、肉用であり、乳そのものを飲用に供することはなかったようである。8世紀に編纂された「古事記」や「日本書紀」には牛や馬にまつわる話が随所に記されている。記紀では神代と現実社会の区切りが必ずしも明確ではなく推定の域を脱し得ないが、日本では牛馬が古代から飼育されていたにもかかわらず乳飲用についての記述は見当たらない。
2.渡来人が伝えた乳利用技術
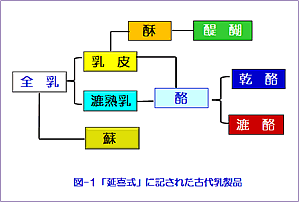
938年、源順(みなもとの したごう)が編纂した「和名類聚抄(わみょうるいじゅうしょう)」には6世紀の半ばに、大伴狭手彦(おおとものさでひこ)が朝鮮から連れてきた中国人、善那が第36代孝徳天皇(645-650)にミルクを献上し、和薬使主(やまとのくすしのおみ)の姓を賜ったことが記されている。この時期は大化の改新のあった頃であり、以後の飛鳥、奈良、平安時代にかけて乳牛院(宮廷内の乳牛飼育舎)や乳の戸(宮中御用の指定酪農家)が設置されるとともに、牛乳からつくった「蘇」を奉納する制度「貢蘇の儀」と延喜式制度(諸国輪番制の貢蘇制度)が確立された。また、同天皇の御代に和薬使主福常が搾乳術を習って乳長上という世襲職を与えられた旨のことも上記の「和名類聚抄」には記されている。927年に藤原時平が著した「延喜式(えんぎしき)」には「蘇」は牛乳大一斗(今の約7.2L)を加熱し、これを大1升(約720ml)、つまり10分の1に濃縮したもので、陶製の壷や木製の籠につめて宮中に奉納したと記されている。「蘇」は今日の発酵クリームまたはクリームに近いもので、牛乳を熱濃縮したものであることから長距離の輸送にも適していた。蘇の他に当時の乳製品として「酪」、「乾酪」、「酥」、「醍醐」などがある(図―1)。「酪」は今日の発酵乳、「乾酪」はチーズ、「酥」は加熱により生じる乳皮を煮詰めたもの、「醍醐」は「酥」を更に煮詰めたバター様乳製品で、衆病皆除の効がある乳のエキスとして尊ばれた。
3.乳は仙人酒?
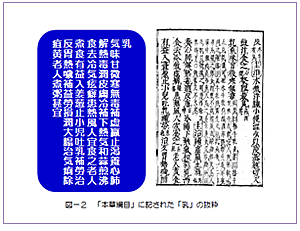
上述した雅な乳製品の製造も朝廷の衰えに伴い徐々に廃れ、平安末期には「貢蘇の儀」も姿を消し、江戸時代の中期まで乳製品についての記載が見当らなくなる。しかし、善那が乳利用技術を伝えたことは我国における乳文化の幕開けであったことには論を俟たないが、江戸時代の中期になって再び乳文化が華を開く上で重要な役割を果たしたのが中国から「斉民要術(さいみんようじゅつ)」と「本草綱目(ほんぞうこうもく)」の二大農書が日本に伝搬したことによる。「斉民要術」は536年頃、北魏の賈思![]() (かしきょう)によって撰述された総合的農書であり、中国に現存する最古で最も完全な本草書で、92編、全10巻から成っている。前出の善那使主の父祖一族が日本に持参したとも云われ、「酪」や「酥」の製法が詳しく記載されている。
(かしきょう)によって撰述された総合的農書であり、中国に現存する最古で最も完全な本草書で、92編、全10巻から成っている。前出の善那使主の父祖一族が日本に持参したとも云われ、「酪」や「酥」の製法が詳しく記載されている。
一方、「本草綱目」は明朝の李時珍(りじちん)によって撰述され1596年に完成した中国の本草学史上においてもっとも充実した農書で全52巻から成っている。初版本は金陵本と呼ばれ、金陵本が刊行されて間もなく日本にも伝搬されている。現在、完全な形で残っている金陵本は世界で7組しか存在していないが、そのうち4組が日本の図書館に所蔵されている。牛乳、乳製品についての記述も詳しく記されている。乳の正体についての記載が面白く、筆者の現代訳では概ね次のようになる。「乳汁は陰血の変化したもので、脾、胃に生じ、受胎せぬうちは下って月経となるが、受胎すると留まって胎児の栄養となり、出産すれば赤が白に変じて乳汁となる」という内容である。つまり、乳汁は本来は赤で、それが白に変わった「化の信」、つまり「化け物」であり、古代中国人は乳汁が化け物であることの本質を隠して「仙人酒」と呼んでいる。なんとも才気煥発的な発想である。さらに、牛乳の効用について記した部分の抜粋を図-2に示した。概ね次のような内容になっている。「味は微かに甘く、飲むと体温を下げるが、毒はない。発汗を抑え、喉の渇きを止める。心肺を養い熱毒を解し、皮膚を潤す。悪寒や熱気を除く。ニンニクと和えて煎沸して飲むと肩こりが治る。解熱にも効果がある。老人は乳を沸かして飲むのがよい。ショウガを入れた乳を小児に与えると吐乳するこがなくなる。しゃっくりを止める効果がある。慢性の身体の痛みを治し、大腸に潤を与え、軟便を改善する。黄疸を除き、老人にとって乳粥は甚だよい」。今日の科学では理解できない部分も多々あるが、これが当時の日本人による乳に関する記載との出会いであった。